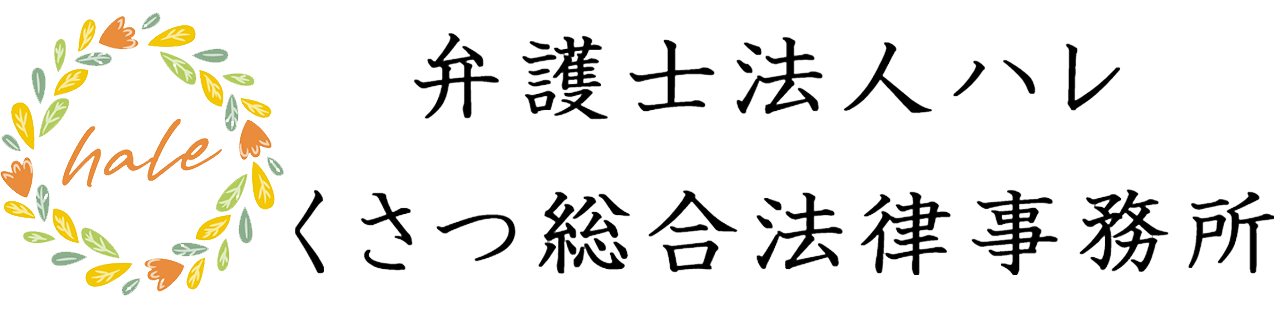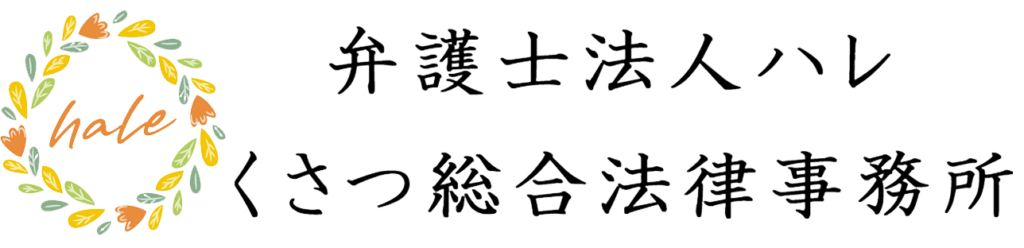医師の離婚
医師の離婚
医師の離婚について
医師は比較的高収入です。高収入であるがゆえに財産分与・養育費・慰謝料等で争いが多くなる傾向があります。
「賃金センサス」と呼ばれる調査によると、医師の平均年収は1,378.3万円で、一般的に年収の高い職業です。そのため、離婚問題に発展した際の医師本人の財産は多く、多いからこそ、争いの種になることがあります。
医師との離婚においては、専門家に頼り、正しい知識を持った上で、より有利な離婚条件で合意をできるようにしましょう。
当事務所では医師の離婚を多く経験しております。安心してご相談ください。
よくあるケース
- 開業しており、配偶者を雇っている
- 預貯金・不動産以外にも高価な資産がある
- 開業医の退職金が財産分与に含まれるのかわからない
- 財産の管理を独りでしているため、詳しいことがわからない
- 職場内で不貞をされた
- 経費が多く、婚姻費用や養育費がきちんともらえるのか不安
Point 1
財産分与
財産分与とは離婚する際にお互いの婚姻期間中に築き上げた財産を平等に分けることを指します。
別居開始時に有している財産を分与するため、医師の場合は、その財産の価額が大きくなります。分与される側としては多く貰いたいところですが、医師側からすると「何故、こんなに渡さないといけないんだ」と問題に発展することが多々あります。
請求が可能なのは、離婚前から離婚後2年間(原則)となります。
・1/2ルールの適用について
しかし、今回の「医師」のように、高収入な職種に夫婦のどちらかが就いているケースでは、その本人の力量による財産であることが多いため、財産分与の基本となる「1/2ルール」が適用されないことも多く、医師側に有利となる財産分与となることがあります。
開業医の財産分与
開業医の場合には、開業資金等、医師自身に多額の負債があることもあります。このケースの場合には、医師の財産はほとんど認められず、医師の配偶者でも多くの財産分与を得ることは難しくなります。
・家族経営している病院のケース
配偶者が開業した病院に勤務していることも多くあると思います。そのような医療機関である場合、経理の面など、医師の財産を正確に把握していることもあります。この場合、配偶者側に有利に財産分与が働くことも考えられます。
・医師ではない配偶者が出資しているケース
いわゆる「出資持分制度」が採用されていた時の医療法人は、出資した額も財産的な価値があるため、分与の適用内となります。例えば、その出資者が配偶者で医療法人に努めている場合、離婚をきっかけに退社、出資持分の払戻請求を行うことも可能です。出資持分の評価が高いほど、医療法人側が多くの財産を配偶者に支払うことにもなり、医師にとって大きなダメージとなることもあります。
勤務医の財産分与について
勤務している医師は、一般的には高収入であっても、開業医ほどではありません。多額の財産を形成していることはなく、配偶者側が財産分与でもらえる額はそう多くはありません。
◎ 事前にしっかりと把握しておきたいこと
財産分与の問題で重要なのは、しっかりと財産を把握しておくことです。
① 保険
医師自身に何かあった時のための保険の解約返戻金は、財産分与の対象となることもあります。配偶者は医師が加入している保険の内容や金額などを事前に調べておくと良いでしょう。
② 絵画や骨董品、アクセサリーなどの高価なもの
高収入の医師は、これらの高価な資産をコレクションしていることも多くあります。趣味として集めている動産も財産として認められるため、評価額に応じて分与されます。
③ 株式、出資持分他
有価証券やゴルフの会員権等も財産分与の対象となりますので、離婚問題や別居開始時に保有している財産を把握して、離婚時にどれくらいの価値になるのかを調べておくと良いでしょう。
④ 退職金や年金など
医療法人に「退職金」があるかないか、厚生年金に加入しているかどうかなどで大きく変わりますが、退職金は財産分与の対象となることがあります。また、年金の場合は年金分割の対象となりますので、事前に把握しておきましょう。
⑤収益不動産等
配偶者の財産をすべて把握するのはなかなか難しいと感じた方も多いと思いますが、財産の内容については開示請求を行うこともできます。調査嘱託や文書提出命令等の法的手段を用いて調べることは可能なので、専門家に相談してみるのも1つの方法です。
Point 2
医師の離婚問題に関するポイント
check
① 財産の帰属の調査
医師は自身の所属している病院等を医療法人としていることも多いです。本来は「医師本人の財産」であるものを「医療法人の財産」として移してしまっていることもあるため、注意が必要です。この場合、医療法人の財産は医師本人の財産とは認められないため、財産分与の対象とはなりません。「医師本人の財産」と思っているものが、しっかりと医師に帰属しているものなのか慎重に見極める必要が出てきます。
check
② 医師の負債に注意する
「財産分与」というのは、プラスの財産だけではなく、マイナスの負債も含め、夫婦で分与する制度です。そのため、医師本人に負債がある場合には、その負債分も含め、夫婦の財産として計算されます。
冒頭でも紹介した通り、医師という職業は一般的に年収の高い職種ですので、財産分与において医師の配偶者に大きなメリットがあるケースがほとんどです。しかし、年収が高くても多くの負債を抱えている医師の場合は得するケースばかりではありません。
そのため、医師本人に開業資金などの負債がないかもチェックしておくと安心です。
check
③ 婚姻費用や養育費の注意点
婚姻費用や養育費は、夫婦の年収によって算出されます。医師の場合は高年収であることが多いため、婚姻費用や養育費を通常よりも高く請求できることがあります。開業医の場合は経費を上手く用いて年収を減らすなどの工夫をしていることで、これらの費用の正確あ読み取りが必要とされます。
まとめ
医師と医師ではない配偶者との離婚問題は、通常の離婚問題よりもさらに、お金のことで揉めるケースが少なくありません。そのため、離婚問題に強い弁護士は勿論のこと、医師との離婚に強い弁護士に相談の上、しっかりと財産分与、養育費をもらえるような取り決めを行ってください。
当事務所は、開業以来、医師と医師ではない配偶者の離婚問題にも多く実績があります。どのくらいの財産があるのか、負債はないのか、養育費はどのくらいもらえるのかなど、是非、専門家である私達にお気軽にご相談いただければと思います。
初回30分限定
離婚・男女問題 無料相談 実施中
些細な事でもお気軽にお問い合わせください
077-599-1882
営業時間: 9:00–18:00
定休日:木曜日
ID @bengoshi-shin
お友達登録は↑をクリック
メールフォーム
メールは上記リンクより(別のページが開きます)
会社経営者(自営業)との離婚
会社経営者となる夫との離婚では、特にお金に関する問題に発展しやすいといわれています。旦那さんは社長であり高収入、奥さんは専業主婦であるケースも少なくなく、財産分与の点で色々な問題に直面する可能性があります。
今回は、社長を夫に持つ奥さまに注意していただきたい離婚問題のポイントを解説していきます。
合意について
婚姻関係の解消、つまり離婚は、「離婚届」を役所に提出することで成立します。お互いの合意のもと提出するものですので、離婚に関して、経営者であるかどうかは関係ありません。お互いの合意さえ得られていれば、どなたでも同じです。
親権者の指定について
未成年のお子さまがいる場合には、子の親権者を指定する必要があります。
一般的に親権者は夫婦の話し合い、合意のもと指定されるものですが、夫が会社経営者である場合は「いずれ、子どもを後継者に」と考えているケースも多く、親権の争いが生じやすいです。
協議、調停でも親権争いが収束しない場合には、裁判で親権を争うこととなります。
家庭裁判の場合は、両親の事情とお子さまの事情を前提として、夫婦の親権者・監護者としての適格性を判断していきます。母性優先の基準、監護の継続性、お子さま自身の意志、きょうだいの不分離、面会交流の許容など、さまざまな基準のもと判断されます。
あくまでも「親権者」として父、母どちらが相応しいかを判断していきますので、夫側の「後継者が必要」という理由は子どもの親権を争うにあたって、母側が不利になることはほとんどないといえるでしょう。
お子さまの養育費について
家庭裁判所、高等裁判所の実務においては、権利者・義務者の収入、子どもの数、年齢に応じた養育費の算定表があり、それをもとに養育費の算定を行います。
経営者のご主人は会社から役員報酬を受領していますが、これは「給与」として認められるため、給与所得者の年収の項目をもとに養育費を算定します。
しかし、ここで注意点が1つあります。
この算定表は、お子さまが「公立の学校に通学していること」を前提としています。そのため、私立の学校に通学されているお子さまの場合は学費の部分で問題に発展しやすいため、注意して進めていく必要があります。
・お子さまの私立通学に関して
私立学校への通学については、既に義務者が同意しているもの、当事者の学歴や職業、収入、居住地域などの状況に合った進学であることとして、適切が金額を加算することがあります。
・お子さまの塾や予備校の費用に関して
塾や予備校の費用に関しても、私立学校と同様に判断されますが、義務者の同意や年収、学歴、生活状況などを踏まえ、学費よりも慎重に判断されることが多いです。
・成人しているお子さまの学費に関して
会社経営者の子どもともなると、大学を目指している、もしくは大学生のお子さまも多いと思います。このお子さまが成人している場合にも、親からの扶養が必要となる「未成熟子」として認められるので、養育費の支払いを請求できるケースがほとんどです。
財産分与について
会社経営者である夫と、その妻の離婚問題については財産分与において注意しなければいけない点がいくつかあります。今回は、Q&A形式によくある質問、問題点をまとめてみました。
事業の資産については、ご主人さまの会社であっても、会社に帰属するものですので、財産分与の対象とはならないのが原則です。
しかし、会社名義の財産である場合にも、一部例外があります。
実質的に「夫婦共有の財産である」と認められる場合には、財産分与の対象となることもあり得るのです。
具体的には、夫婦のみが出資している会社であり、会社の資産と夫婦の資産が完全分離しておらず、まとめて管理されているケースなどです。
離婚を理由として、雇用関係を終了させることはできません。つまり、仮に解雇を命じられたとしても、奥さま側は解雇無効等を主張することが可能です。
しかし、離婚した元夫の会社に働き続けるというのは現実問題として非常に難しいと思われます。
今後の雇用契約についても、離婚前にしっかり話し合いの場を設けるのが良さそうです。
会社の経営者自身が株式を保有しているケースは、そう珍しくありません。また、婚姻後に取得した株式については、自社の株式であっても夫婦の共有財産として認められるので、財産分与の対象となります。
しかし、夫側からすると、離婚する妻に自社の株式を分与するのは、会社としても大きな問題となります。そのため、妻がこの株式の分与を希望したとしても、会社経営に関与するのは回避したいため、株式の分与を拒絶することになるのが一般的です。
妻からしても、特に会社の経営に携わりたい等の特別な思いがない場合には、ほとんどメリットはないと思います。
自社株式の分与を行わない代わりに、その価値を正しく評価し、その評価額の1/2を金銭で受領するなどの方法が双方にとって良い策になるのではないでしょうか。
年金分割に関して
会社経営者の夫が厚生年金に加入している場合、妻は年金分割の手続きをすることができます。
また、厚生年金の他に私的年金に加入している場合もありますが、この私的年金は対象外となりますのでご注意ください。
離婚の慰謝料に関して
「慰謝料」とは、主に精神的な苦痛や負担に対して支払われるものになります。
例えば、夫婦のどちらかの不貞行為やDV(暴力)などがあります。
今回は、会社経営者の夫が不貞行為をして、離婚に至った場合の慰謝料についてお話していきます。
慰謝料の額は、さまざまな事情を総合的に判断して決められるので、今回の「会社経営者であること」も1つ、慰謝料額に反映される事情となります。
しかし、一昔前は当事者の社会的地位や支払い能力を大きく判断材料としていたものの、現在は、慰謝料算定の事情の1つとして、大きく材料としないことが多く、高額な慰謝料が取れるとは限りません。
夫が社長である、高収入であるという事情はあるものの、一般的な会社員の方が不貞行為をして離婚に至った事例とそう変わりない慰謝料となるのが一般的です。
その他、会社経営者の夫との離婚問題について
会社経営者といっても、その形態はさまざまで、妻の実家の家業を継いでいるケースも少なくありません。
1つ事例として、夫と妻の両親が養子縁組をしている場合の離婚についてをご紹介します。
この場合、夫と妻の離婚で、養子縁組が解消されることはありません。養親子関係を終了するには、両親から、離縁手続きを行う必要がありますので、それがない限りは養子縁組の関係が続きます。
まとめ
今回は会社経営者とその妻の離婚問題について詳しく解説してきました。専門的な知識のないままに手続きを進めると損してしまうケースも生じますので、まずは専門家に相談することからはじめましょう。
初回30分限定
離婚・男女問題 無料相談 実施中
些細な事でもお気軽にお問い合わせください
077-599-1882
営業時間: 9:00–18:00
定休日:木曜日
ID @bengoshi-shin
お友達登録は↑をクリック
メールフォーム
メールは上記リンクより(別のページが開きます)